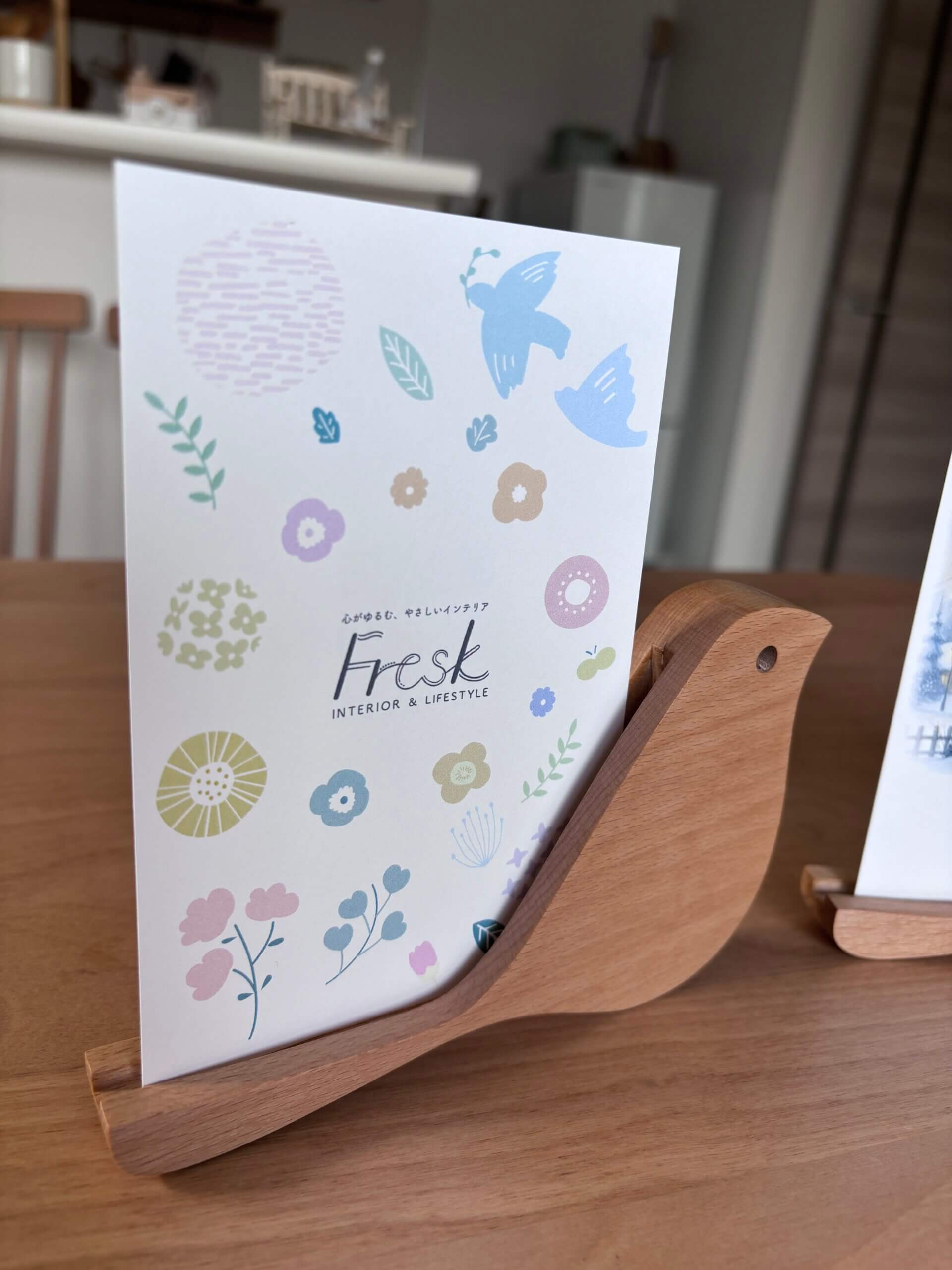公開日:2024.03.09 更新日:2025.07.11
目次
事業立ち上げについての考えていた事と実体験
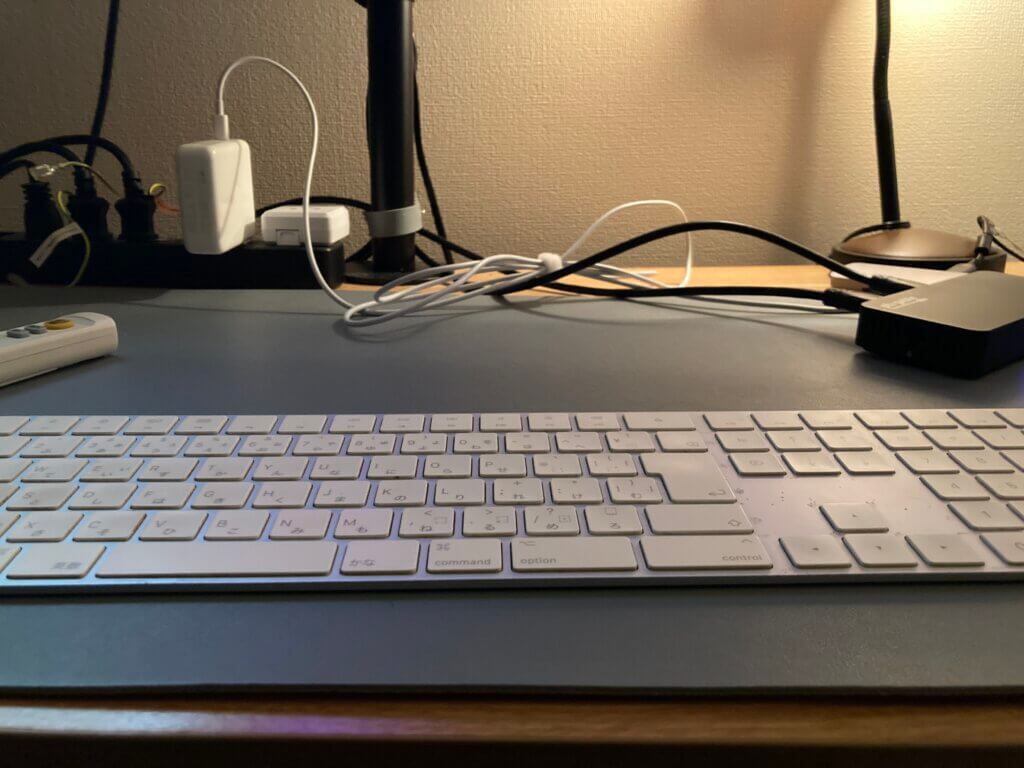
今日は「事業立ち上げについての考察と実体験」といったテーマで、コラムを書いていきます。
ソラノデザインはWEB制作・マーケティングコンサルティング事業がメイン事業なのですが、
去年からEコマース(通販事業)のほうも力を入れ、
ようやくEコマース事業の方もブレイクイーブン(損益分岐)を超えそうな段階です。
そんな弊社が「2事業目立ち上げ時に考えていた事や実体験」といった本題に入っていきたいと思います。
創業期、2事業目に手を出す前に考えていたこと。
結論、2事業目に手を出す前に考えていたのは2軸です。
- AIによる業界の変化が数年後起こりそうな事
- そもそも「ビジネスモデルの選定」で狙える年商や利益が決まる事
の2つです。
1のAIの到来による業界変化については、別のコラムでも書いたので、
今回は割愛します。
「ビジネスモデルの選定」で狙える年商や利益が決まる事
そのため2番の、「ビジネスモデルの選定」で狙える年商や利益が決まる事、
について解説していきますね。
「“どのビジネスモデルで戦うか”というのは”どの国で生まれるか”くらい人生が変わる」
これは結構ビジネスパーソンの間ではよく聞く話です。
色々なビジネスモデルをインプットするために、
20代後半、IRを何となく見ていた時期がありました。
そこで気がついたのが、この、
「そもそも”どのビジネスモデルで戦うか”というのは”どの国で生まれるか”くらい人生が変わる」
ということです。
2事業目に手を出すきっかけにもなりました。
一番わかりやすく、「売上のトップライン」という点から見ていきましょう。
例えば現在弊社がやっているWEB制作事業は、1人あたりの売上のトップラインは低い業界です。
例えば案件獲得もデザインもプログラミングもディレクションも一人でできます!
といったスキルを持った知り合いに、
「1人で月何本のWEBサイトを作れますか?」と質問すると、
どれだけハイスピードな人がハードワークしても3本 / 月なんですよね。
となると、一般的なWEBサイト単価が、80万円だということにすると、
どれだけ優秀でハイスピードな人が集まってハードワークしても、
月の1人あたりの売上は240万円が上限。
実際に石川県の採用市場の人材は1本〜1.5本 / 月くらいの温度感なので、
1人あたりの売上は80万円〜/月くらいが上限のビジネスモデルです。
このWEB制作のビジネスモデルで年商3億、5億、10億を目指し維持していくのは、
先輩の言葉を借りますと”修羅の道”だと思っています。
個人の年収といった観点でも、この業界で年収2000万を目指そうとなると、
自分か部下、どちらかが疲弊する構造になりますね。
「受注単価を上げれば良い」という考え方をする方もいらっしゃるかもですが、
労働集約型のビジネスモデルでは、
「受注単価」と「市場の相場」が一定離れてしまうと、
結果売上が伸びても営業利益は変わらない、という現象が起きるんですね。
なぜかといいますと、受注単価を上げるためは、
営業リソースとブランディング関連固定費も勘案しないといけません。
簡単にいうと、受注単価が上がっても営業人材の人件費が追加で必要だったら意味ないぞ、
って話ですね。
むしろマネジメントコストで決済権者の精神的疲労のほうが蓄積しそうです。
もちろん1本のサイトを120万円〜200万円などで受注できれば、
それこそ売上・粗利は上がりますが、
そのために必要な営業マンの人件費、
当然単価が上がると下がる商談のクロージング率、
ブランディングのための建屋への投資、
色々と勘案すると、
販管費や固定費が嵩み、結局営業利益はそんなに変わらないというのが、
市場の相場と、自社の相場の関係性です。
もうひとつ言及するならば、値段に応じてクライアントさんの期待値が高まるので、
工数も比例して増えてしまうなどですね。
わかりやすくtoC商材に例えるなら、80万円の車と、200万円の車、
2つが同じスペックだと、
中長期的で見ると、確実に前者に顧客が流れ後者の企業は顧客を奪われていきます。
制作コストは、費用に比例して上げていかないといけません。
顧客の期待値に応える事は、中長期的にビジネスをスケールさせていくにおいてとても大切です。
一見うまく行ってそうなのに、そこまで伸びない場合、
大きい事を言いすぎて期待値を自分で上げすぎてる、
実際に言っているサービスの結果と提供できてるサービスの結果に乖離があるため、
スケールしきらないって、たまにあるんですよね。
サービスを提供する前に再現性のある期待値を提供することは本当に大切で、
結論、どのビジネスをするにも、顧客の期待値やCPA、ROICは勘案しなきゃ、ということです。
私個人的には、原価管理と同じくらい、
「期待値管理」「CPA管理」「ROIC管理」の3軸は事業において大切だと考えています。
特に期待値は大切に考えてまして、
どの程度の期待値を感じさせ満たしていくか、は各事業よく考えたりします。
結論、WEB制作事業では、
受注単価を上げても受注コストが上がると、
利益に対するインパクトはほとんどないんですね。
繰り返しになりますが、WEB制作事業で3億、5億、10億と目指すのは修羅の道だなと感じています。
事業に対する深い愛情がないと、乗り越えられない壁です。
不動産事業などでは年商10億の企業さんなんてざらにいますが、
WEB制作事業で10億企業つくっている会社の社長さんがもし皆さんの知り合いにいらっしゃれば、
その方は本当にすごい方だと思います。
単価の高い東京で集客チャネルを作り工場は石川などの地方でやる、
というのは再現性がある単価UPな気がしますが、
その座組を作るのも多分2〜3年は必要で、
私個人の求める速度に対しては「3年は地味に長い」というのが正直な感想です。
AIもありますしね。
そもそも私の起業した時期は、業界的に5年〜10年遅いという感覚もありましたし、
WEB制作の事業を伸ばす事には当初からネガティヴな感情を持っていました。
この事業は、箱は小さく、世の中に役立つ事業にしようと。
なにより「これくらいの年商で終わるなー」という着地点を見るには、
まだまだ20代だった当時の私にとってはある種「諦め」のようで、
もっともっと視座を上げていきたいと感じていました。
自分の視座を上げるためにも、2事業目は元々選択肢として考えてはいました。
ただ最初に手を出す事業としては受託事業のメリットも感じていました
ただWEB制作事業にもメリットはありまして、
- 受託は初期コストがほぼいらない(PCと自分のスキルがあれば起業可能)
- 原価がほぼ人件費のみ
- Jカーブがほとんどないに近い(初期に赤を掘るビジネスモデルではない)
- 経験が増え自分の成長に対してインパクトが強い
といったメリットもあります。
つまり“少ない種銭”で”目先の現金”を生み出す力はある事業なんですね。
1事業目に何かするのであれば、受託ほど良いビジネスモデルはないです。
最初種銭もなくノーファイナンスでやるとなると、
投資できる資産は「時間」しかありません。
種銭のない若手の私が最初に作る事業としては、
「時間」を投資し「リターン」を得られる受託ビジネスモデルはとても有益でした。
投資できる資産としてキャッシュはなかったのですが、時間は平等にありますからね。
偉そうに書いていますが、今回書いた内容は、
結構よくある考え方・座組だと思うんですよね。
最初は受託でキャリアをスタートして、そこでの人脈や知識、種銭をもとに、
新しいビジネスモデルにチャレンジする。
私の周りでも同じような動きをしている事業家さんが沢山いるように感じます。
デットでの借入はビジネス人生における「ここぞ」というタイミングに与信をとっておきたい。
エクイティで株式放出はイヤ、投資家に決裁権を渡したくない。
そんな経営者さんは意外と多いのではないかなと。
2事業目に手を出す際に考えていたリスク
そういった設計が頭の中にあったので、
もともと新規事業にはポジティブだったのですが、
ただ反面、リスクは頭をよぎっていました。
- 色々手を出すべきじゃない説。1事業で10億までいける、色々な事業に手を出してる人ほど意外と数字持っていない。
- 1事業当てる打率はだいたい10打数1安打、そんなに簡単に当たらない。
この2つは凄く気にしてましたね…。
よくあるパターンで。
受託がうまくいって、調子に乗って、新規事業に手を出して、
こけて、「結局受託が一番稼げた」って気がついて戻ってくる。
数年間を無駄にしちゃう。
または尖ったビジネスモデルで起業したけど、
結局マネタイズポイントは受託に着地してない?など。
これけっこう事業家あるあるでして、
私もそうなるんじゃないかと不安は抱えてましたし、今でも抱えています。
「色々手を出すべきじゃない説」はやっぱり先輩方からも言われましたね。
4事業くらい持っているような大きな会社でも、
売上の8割は●●事業部、みたいな事も多いです。
また、繰り返しになりますが、かなりハイレイヤーな先輩でも、
大体事業立ち上げの打率は1〜2割くらいかなっていうのが体感です。
結局2事業当てる、2事業大きな売上を出すって、わりと再現性がないんですよね。
2事業目をやるリスクみたいのはそういった側面で感じていました。
正直今の2事業目の立ち上げがうまくいきそうなのは、
アサインしてくれたメンバーの感覚と事業の相性が良かった事など、
運要素もかなり大きいなと思っています。
なので当時は、リスクヘッジのやり方の一つとして、
何が当たるかなーと、1期目から色々仕込んで、新規事業の種は蒔いてました。
しかし実際に少し芽が出たドメインがあった時に、
「キャッシュやリソースを費やして水を与え続ける」
そう決断し切るまでには数ヶ月かかりました。
ただ結論、もっと上を目指したいと思いましたし、
正直AIの登場も後押しになり、2事業目にリソースとキャッシュを割き始めたのが去年です。
なぜ2事業目をEコマースにしたのか

前述の通り、
「このビジネスモデルのトップラインがどれくらいか」という視点で事業を見ていたので、
元々資本集約型のビジネスモデルには目をつけていました。
しかしそれだけで決定できません。
できる限り打率を高めるために、私がビジネスモデルの選択で重要視したのは「再現性」です。
- 自分のアセットで再現性がある
- 自社のキャッシュでゼロイチが終わる
- 市場に参入の余地がある
この3軸を勘案して2事業目をEコマースにしました。
ひとつひとつ簡単にまとめていきます。
自分のアセットで再現性がある
これまでWEBの領域のスキルを学んできた私が、
全く関係のない領域に手を出すのは打率が下がると思いました。
例えば小金持ちになって、自分の店を持ちたいと思って、
全然関係ない飲食ビジネスに手を出して後悔する、
みたいな事ってよく起きると思っています。
今回の事業立ち上げは夢や承認欲求ではなく、
再現性を重要視したかったので、
これまで学んできたスキルを活かせるビジネスモデルに絞りました。
自社のキャッシュでゼロイチが終わる
これもタイトル通りですね。
テストマーケティング費用も合わせて、
そもそもスケールにどの程度お金がかかるかは当然大切です。
ただ私の場合は計算をミスり、
当初考えていた集客チャネルや仕入れルートに変更があり、
在庫モデルで進めることになった結果、
現在かなりお金はカツカツで事業を成長させています。
お金の計算 = 体力の計算、とても大切です。
市場に参入の余地がある
私はプロダクトアウトではなくマーケットインで戦うタイプの事業家なので、
ここはとても重要視して市場選定しました。
具体的に言いますと、
「ある程度成熟しつつある市場で、集客チャネル的にはまだ隙間がある市場」って、
私のようなWEBをやっている人間は狙っちゃうんですよね。
ここは時間をかけて、この角度でも隙間がある、
それがダメでもこの角度でも隙間がある、といったのは見て事業を選定しました。
これ結構需要もあるテーマだと思いますので、何れ別のコラムでまとめてみようと思います。
「事業成長」は属人的でも構わないが、「属人的に作った売上」に価値はない。
最後にもうひとつ、Eコマース事業を立ち上げた理由があります。
それは
「事業成長」は属人的でも構わないが、「属人的に作った売上」に価値はない。
という価値観が、私の中に根強くあった事です。
結論から言いますと、「頑張っている人が報われる会社を作る事」が私個人のビジョンなんですね。
WEB制作事業の方は、端的にいうと属人化が激しい事業で、
デザインが上手い人、プログラミングが上手い人、マーケティングが上手い人、
が社内に存在し活躍する事で、売上・利益が成長します。
優秀なスタッフの承認欲求・自己肯定感といった意味では、
こういったビジネスモデルは良いのかもしれませんが、
- 誰かが長期休暇をとっても売上が落ちない
- 誰かが離職しても売上が落ちない
- 誰かが早退しても売上が落ちない
などの観点で考えるとよくないビジネスモデルです。
働き方改革、ジェンダー平等、
時代の流れに合わせたいというのもありますが、
私としては個人の能力などではなく、
“頑張っていて、現実が見えている、倫理観のある真面目な人かどうか。”で給与が決まる組織が理想だなという価値観があったので、
そのためにも「売上は属人化させない」ことが重要だと考えていました。
事業成長はどうしても属人化するので、そこはしょうがないと考えていますが、
「売上の属人化」については、私は一事業家として、良い事だとは考えていません。
そういった側面でも、Eコマース事業は魅力的だと感じていました。
まとめ
今回は事業立ち上げ時に考えていた事をまとめたコラムでした。
次回は、具体的な集客チャネルや立ち上げの際に苦労した事、
ぶつかった壁とそれを乗り越えた方法等を書いていきたいと思います。
今後ともソラノデザインを、どうぞ宜しくお願い申し上げます。