公開日:2025.09.30 更新日:2025.10.10
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
ソラノデザイン合同会社、代表の角田です。
ソラノデザインの2事業ともに、この数年でようやく少しは胸を張れる規模に育ってきました。
本日は『【2025年版】ソラノデザインが考えるWEBマーケとWEBでの事業作り』というテーマで、
これまでの私の学習の総集編的な記事を書こうと思います。
事業の現場で実際に効いた、知見・体験だけを書いていく記事です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
目次
1次情報を中心とした現実から逆算して事業設計を行う。
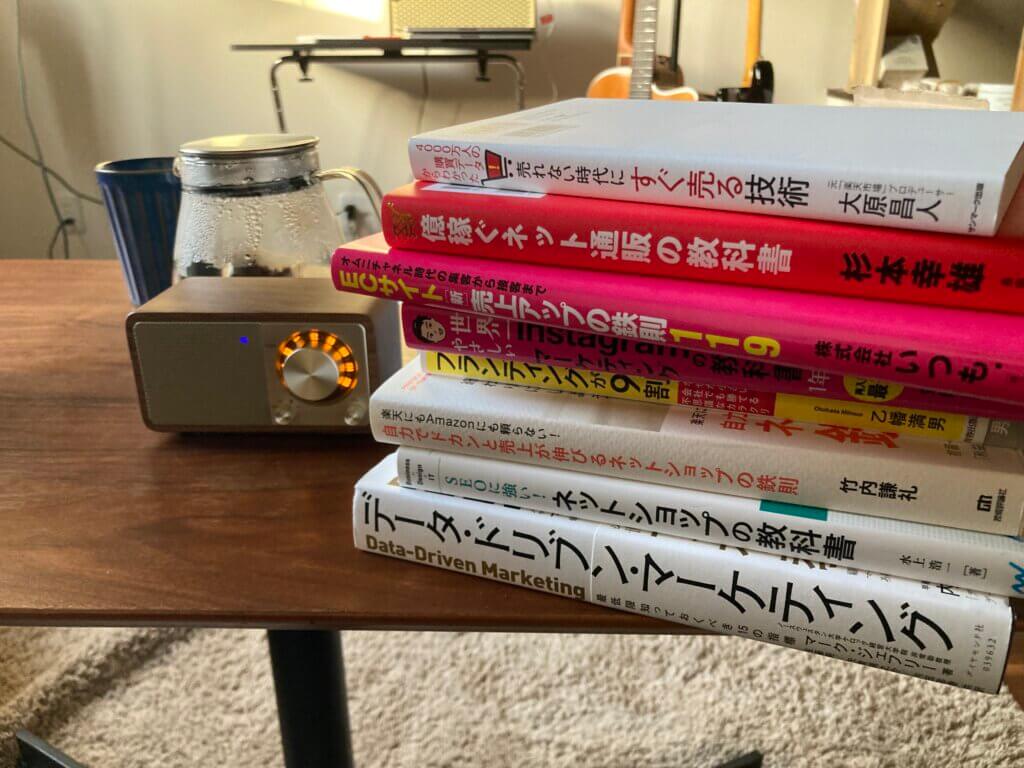
事業を立ち上げる上で、私は一番大切にしているのは、「現実を見ること」です。
ブランディングであれマーケティングであれ、これが土台だと私は考えています。
例えば私は元々エンジニアなので、
「Next.jsやRailsで作った高度なプロダクトこそ価値がある」というバイアスがかかりやすかったりします。
自分の培ってきたスキルが、世の中に対してインパクトがあると思いたいからです。
デザインが得意な方は
「良いデザインのWEBサイトを作れば売れるはずだ」というバイアスがかかるでしょう。
YouTubeに出てる経営者に憧れてる方は、
「YouTubeのあの人の言う通りにやろう」というバイアスがかかります。
しかし、どちらもプロダクト次第では正しくも間違いにもなるという現実を、
とりあえずは、認めなければいけません。
WEBが「プロダクトのプロモーションを担う道具」として、いま何を求められているのか。
理想ではなく現実に合わせて「解像度を」上げることが大切です。
ひとつ分かりやすい事例をあげますと、
昔、ある高級路線の商材LPで、「洗練された高級デザインが正解」と思い込んでしまったケースがありました。
しかし、洗練された高級デザインなのに、売れない。
商材も高級路線なのに、なぜなのか。
当時、混乱したのを覚えています。
結果、少し古めかしい和紙背景を使った、
デザイナー目線で言えば“ださい”デザインに切り替えると、売上が跳ねた。
なぜなのか。
実は実際の顧客は年配の方が多く、
顧客にとっては2000年代初頭のようなWEBデザインに、親しみと安心感があったんです。
これは、こちらが勝手に「高級商材だから、高級なデザインが受けるはずだ!」と思ってしまい、
うまく商品を販促できなかったわかりやすい事例です。
プロモーションに携わる以上、まずはバイアスを疑う。
理想に傾かない。
顧客の「現実」に寄り添う。
まず何をやっても、
ここを外すと、以降の施策は全部ズレてしまうと思い、最初に記載しました。
領域選定力とTAM・SAM・SOMの把握

領域選定は、事業でもWEBマーケでも最初に決めるべき重要な要素です。
SEOをハックしても、SNSをハックしても。PPC広告をハックしても。
媒体のハックだけで伸ばせる売上には限界があります。
SEOや広告で短期は伸びても、プロダクトと市場構造が噛み合っていないと、年商の桁は大した額にならないんですね。
だからこそ、最初に、
「攻めるべき領域か」を見極める事が、
事業であれマーケ施策であれ、ブランディングであれ、とても重要です。
私はこのフェーズで、定量調査の前に、
マクロ型ジャーニーマップ・ミクロ型ジャーニーマップを作る前に、
定性調査を行うことをお勧めします。
SNSを小さく回してフォロワーの反応を拾い、オフラインでは泥臭くインタビューを重ねる。
机上のSTP分析よりも、一次情報で「刺さる瞬間」を掴むほうが早い。
マーケティングに携わるものとしては、このフェーズでもカッコつけて、STP分析をしたくなっちゃうんですけどね。
もちろんSTPも無駄にはならないのですが、個人的に最短距離は「一次情報を定性で得ること」だと考えています。
また、こんな事をいうと元も子もないですが、
領域選定には「運」の要素も正直あります。
働いてお金を貯めて、
良いカードを引くまで試し続ける自由を、
自分に与えられるかどうかも大切です。
TAM・SAM・SOMの把握
ひとつこの章で触れておきたいのは、「ブルーオーシャンだからOK」「領域特化だからOK」という考え方は、危険という事です。
誰もやっていないのは、儲からないから、構造的に成り立たないから、というのは、本当に事業あるある。
また、市場規模を金額だけで見るのも危険だと考えています。
例えば、4億円規模の小さな小さなニッチ市場で10%を取っても4,000万円。大きくはない。
50%を取れれば2億円ですが、現実にそのシェアを取り続けるのはほぼ不可能です。
私は市場調査の際、その市場の規模を「金額」で見るのではなく、
TOP20の企業・ブランドの顔ぶれと、それぞれの売上を必ず見にいきます。
業界の1位から20位までを俯瞰し、自社が20位・50位・100位に入った際の売上を現実的に見積もる。
1位になれるなんて夢を見ず、20位や30位でどれくらいの利益があるか。
そもそも1位の企業はどれくらいの売上・利益なのか。
市場規模が数千億〜数兆の場合は、
TOP100に入ればどれくらい利益が出るかも見にいきます。
ここで無理があるなら、あまり収益性がないなら、
潔く“戦う領域”を変更します。
市場規模の数字や、ブルーオーシャン戦略などといった言葉に騙されて事業をはじめると、
いつの日か 「あれ。この市場でどれだけ頑張っても、報われない。」 と気がつく日がやってきます。
そうならないために必要な概念が、TAM・SAM・SOMです。
TAM(Total Addressable Market)・・・・理論上の最大市場規模
SAM(Serviceable Available Market)・・・実際に狙える市場規模(地域・ターゲットを絞ったもの)
SOM(Serviceable Obtainable Market)・・・さらにその中で実際に取れる市場規模(シェア)
この設計や理解が甘いと、間違ったマーケティング施策や事業領域に、数年間時間と労力を突っ込んでしまいます。
個人的には、才能豊かな人ほど、 TAM・SAM・SOMを正しく把握し、 才能にあった稼ぎや年商を獲得してほしいと思っています。
しかし意外と、ブルーオーシャン戦略・イノベーター理論など、 YouTube映えする知識ばかり席巻する今の世の中では、
TAM/SAM/SOMの概念は見落としがちです。
同じ労力と才能でも、領域選定でミスがあれば、
努力が利益に跳ねてきません。
それどころか、明らかに私より才能がある方が、
領域選定で遠慮しすぎて、利益は私より低い、
なんて事例も見た事が何度もあります。
とはいえ、GAFAや大手が来る領域も避けなければいけないので、
選定は非常に難しいです。
例えば、画像から文字を読み取るアプリで事業を伸ばしていた会社がありましたが、
今はiPhoneやMacに、無料でその機能が搭載され、
その会社は大打撃を受けました。
「領域選定力とTAM・SOM・SAMの把握」
誰もがめちゃくちゃ大事にするべきタスクです。
リード獲得の導線管理から事業を設計する

個人的に見ていて、多くの失敗は、「プロダクト → プロモーション → 販売」という順番から始まると考えています。
勝つ順番は逆です。「導線(ファネル) → タッチポイント → コンテンツ → プロダクト適合」。
マーケットインが必ずしも正義だとは思いませんが、
たとえプロダクトアウト寄りの事業であれ、
「考え方としてのマーケットイン視点」はとても大切です。
どのチャネルから入って、どこでリードに転換し、何で教育して、どの不安を外し、どんなクロージングをするか。
そして、次回購入までをLTVの設計としてどう埋めるか。
弊社通販事業の場合は、入口を広告で広げるより、購入後の体験に投資したほうがROASが安定しました。
ノベルティや同梱物、ステップ配信、FAQの差し込み。
これらが積み上がると、入口の“無理押し”がいらなくなる。
つまり、ビジネスは「入口の拡大」よりも「導線の最適化」で伸びるのです。
ここ最近少し面白かったのが、同じCPAの広告でも、クリエイティブによってはACS(客単)とLTVに変動があったこと。
広告やWEBデザインが与える影響範囲として、エンゲージメント率やCPA、CTRという数値は良く見られますが、 ACSとLTVまで見て導線設計ができれば、事業構築としてはかなり堅いなと思いました。
こちらについては、まだまだ私も道半ばですが、探究していきたい指標です。
『構造設計』で事業を運営すること

この章はかなり抽象論になります。
私もこの1年ほど、経営に取り入れてうまく行った概念なのですが、 『構造設計』で事業を運営すること をとても大切にしています。
この考え方に至ったのは、マネジメントや組織作りを本業としている友人から、
コンセプチュアルスキル・カッツモデルという概念を教えてもらってからです。
カッツモデルでは、経営には大きく3種類のスキルが求められると言われています。
- テクニカルスキル(専門スキル)
- ヒューマンスキル(人間関係のスキル)
- コンセプチュアルスキル(概念化スキル)
この中で私が特に強く意識しているのが「コンセプチュアルスキル」です。
つまり、目の前の課題や現象を「構造的に捉える力」。
事業というのは、日々のオペレーションや施策の積み重ねで進みます。
しかし「一見上手くいっているように見えるが、構造的には破綻している」ケースは驚くほど多いです。
例えば、
- 広告に頼り切っているが、LTVが低く赤字を垂れ流しているEC事業
- 案件単価は高いが、営業依存度が強すぎて再現性のない制作事業
- リードは取れているが、ナーチャリング設計がゼロでCVに繋がらないマーケ施策
こうした「構造の歪み」は、表面上の数値だけを追っていると気づけません。
しかし一度構造的に図解し、どこがボトルネックかを把握すると、打ち手の優先順位が明確になります。
私は実務で、次のようなフレームをよく使っています。
- リード獲得 → 育成 → 販売 → リピート という流れを図に落とし、各段階の数値を整理
- CAC(顧客獲得コスト)、LTV(顧客生涯価値)、フリークエンシー(購入頻度)を主要KPIに設定
- 「この構造なら利益が出続けるか?」をシミュレーション
例えば弊社の通販事業では、広告での新規獲得よりも「ノベルティ施策でのリピート率改善」の方がLTV構造に与えるインパクトが大きいと分かり、そこに投資を集中しました。
結果として、広告費依存度を下げながら安定した売上を積み上げることができています。
ソフトスキルでも大切な構造設計
ここまで書いたのは、ビジネスモデル面での「『構造設計』で事業を運営すること」についてです。
しかし私が言う「構造設計」という概念が一番活躍してると感じるのは、 「人を巻き込む」といったソフトスキルの面です。
例えばSNS投稿をお願いしているフリーランスの方がいるとします。
その方の1案件の相場が5万円だとしましょう。
そしてその方は、毎月50万円の収入を得ているとします。
その方に6万円の案件を、毎月6件、発注していたらどうでしょう。
6×6で36万円、その方の収入の過半数を、弊社からの発注で埋めている形になります。
この構造ですと、「その方が真剣に仕事に取り組んでくれる構造」になります。
真剣に取り組んでもらうように、感情的に訴えたり、厳しく接したり管理したりせずとも、
「発注を切られると、月収の半分が消えるのはいやだし、こんなに単価が高い案件がなくなるのは損だから頑張らなきゃ。」と、
自制心が働く「構造」になっています。
基本的にスタッフであれ、フリーランスの方であれ、 「クライアント様の事業を真剣に伸ばしたい」と心から思っている子は少ないと思います。
なぜなら皆、基本ベースは、生活のために、働いている。
あと、私のようにプライドが高い男性で多いのは、
承認欲求のために働いてしまったり、
アイデンティティの確立の手段を仕事にしてしまっていたり。
「事業を伸ばす」と言うタスクに、意外と100%の純度で取り組んでいる人は少ないんですね。
だからこそ、「構造」で「私を含めた全員が頑張る」ようにする事が大切です。
逆に私が何か失敗したとき、振り返ってみれば「構造設計」が破綻している事が多かったです。
例えば解雇の不安がない「正社員」という雇用形態の方に、
最初はこちらからGiveしようと、最初からその方の粗利に見合わない、高い給与を払ったこともありました。
社員さん目線で「頑張らなくても高い報酬をもらえる」構造になってしまえば、 そりゃ頑張らなくなるでしょう。
当時は「なんでもっと必死に頑張らないんだ!」なんて思ってしまってましたが、
今振り返ると理解できます。
「頑張らない構造」を経営者が作ってしまってたんです。
起業する前、フリーランス時代もそうです。
他のフリーランスは2万円でやってくれるのが相場なところ、 特にクライアント様にメリットがないのに4万円の見積もりでやっていても、 構造的にいつか発注が途切れます。
当たり前です。
こういった「間違った構造」は、 人間力や、気に入られ力、人脈力などで乗り切れたりもしますが、
「ビジネスとして設計する」となると、話が違います。
ビジネスは破綻しないよう、構造設計だけで回るよう、構築しなければ、 大きくなりませんし、小さく終わります。
これは自戒を込めてなのですが、 「正しい構造」で経営するよう、心がけていますね。
構造を作る上で、人間性も大切に。
もう一つ個人的に、
「スタッフに愛情を持てるかどうか」も「構造として」大切にしています。
心の底では見下している、大切にしていない、興味を持っていない、でも演技をしている。
これって大体、バレるんですよね。
チームメンバー同士が、相手に興味や情を持てないのは、チームがうまくいかない構造です。
人は自分に興味を持ってくれる人が好きですし、
自分を大切にしてくれる人が好きな生き物です。
これは上司であれ部下であれそうなんですが、
私は面接の際に「何かあった際でも、ちょっと損してでも、この人たちを大切にできるか。」はとても大切にしています。
とても感覚的なことなんですが。。
反面、それが無理だと思えば、そのチームは解散します。
これは意図的にと言うより、お互いを大切にできないチームが、残ることは基本、ないと思っています。
お互いがお互いのモチベーションや働き方、置かれた状況やアイデンティティに、興味を持てるか。
ハックや演技では出せる年商に限界があると書きましたが、チームビルディングでも同じだと思います。
興味を互いに持てるチーム作り、そういう構造を日々のマネジメントや採用で培うこと、大切ですね。
余談:儲かる構造
構造の話で、
余談ではありますが、私はまだ、
「儲かる構造」で経営ができた事がありません。
あくまで、私の属人的なスキルや労力で稼ぐことはできていますが、
「構造で稼ぐ」ことは、厳密にはできていません。
SNSの黎明期にSNSに取り組み、競合が入る前に認知を上げていく・・・・・儲かる構造です
青汁をリピート商材と捉え、さらにTwitter広告の黎明期にCPAを安く、青汁ユーザーを獲得、リピートしてもらう・・・・儲かる構造です
時代の流れ、市場、商材、チャネルを正確に捉え、
「儲かる構造を設計して儲ける」
やりたくてもやれていないのが、この「構造で儲ける」という方法です。
30代のうちに達成してみたいものですね。
ブランドコンセプトを貫く

話を戻します。
事業を長く続けていくために、どうしても外せないのがブランドコンセプトを貫くことです。
ブランドコンセプトとは、単に「オシャレな言葉遊び」ではなく、事業全体の意思決定を縛る「軸」そのものです。
ソラノデザインの社内事業の会議では、
『ブランドコンセプトは、社長より偉い。』とスタッフに伝えています。
たとえばEC事業で「ブランド・コンセプト」を決めると、
- 商品選定
- サイトデザイン
- 梱包方法
- SNSでの発信トーン
- 顧客対応の姿勢
これらすべてにブランドコンセプトが反映されます。
ブランドやプロダクト作りを、簡単に捉えてはいけません。
「その場で売り切り系」のビジネス、アフィリエイトなどのビジネスは、
指名検索は必要がない = 比例してブランド・コンセプトも必要ないのかもしれません。
しかし指名検索が必要なプロダクトでは、
この「ブランド・コンセプト」がないと乗り切れないと確信しています。
指名検索を作る、ブランドを作るのは本当に難しい。
社内メンバーの思い、プロモーション、プロダクト、プレイス、プライス、
全てが一つのブランドコンセプトを向いて、
「数年間」同じ思いを貫き、一点突破する。
ここまでやらないとブランドやプロダクトはできません。
経営をしていると、ブランドコンセプトがない場合に、
特に懸念なのが、社内メンバーが「判断軸」を失うことです。
これは一人で事業を作っていた頃にはわからなかったデメリットでした。
日々のSNS投稿、
チラシのデザインからSNSのデザイン、
メールでのやり取り・・・・
ありとあらゆる面で、
「ブランドコンセプトという軸が決まっている組織」と、
「個々人の能力や価値観で運営する組織」では、
中長期で見た時に、本当に大きな差が生まれます。
最短で遠くに行きたいのであれば、
ブランドコンセプトは大切ですし、
どれだけ少なくとも半年以上、
1つのブランドコンセプトを貫いてみる、
そういう覚悟と努力が必要だと、私は感じています。
テストマーケでは色々やることが大切ですが、テストはあくまで、テスト。
事業作りと、テストマーケは別なんです。
どれだけ短くとも半年、1年スパンで、
ブランドコンセプトを貫く覚悟が、事業家には必要だと感じています。
そういうコンセプト、なかなか見つからないんですけどね。
一つの目標のために、大人が集まって、揉めようが赤字だろうが、借金をしようが、突き進んでいく。
そんな「何か」というのはなかなか見つからないものです。
しかし強烈で熱量のあるコンセプトが、事業作りには、少なくともゼロイチには、必要だと確信しています。
事業責任者が顧客を理解すること/ペルソナ設計の深さ

ここまでで理解した、領域理解、市場理解、ブランドコンセプトを、
日々の意思決定に落とし込むために。
めちゃくちゃ大切なのが、
事業責任者自身の「生身の顧客理解」だと思っています。
これは私自身の反省もあるのですが、
部下の報告や、代理店レポートや集計ダッシュボードは大事ですが、肌感覚がない。
私は、今は四半期ごとに自分の足で一次情報を取りに行っています。
既存のお客様に30分話を聞き、失注の方にも頭を下げて理由を聞く。
購買直後に「なぜ今?」の5分アンケートを差し込む。
SNSのDMとコメントは毎朝まとまって読む。
数値の上下の裏にある言葉の癖や、悩み方の温度を拾う。
TVを見る時間があれば、ヒートマップツールを見にいきます。
ペルソナは綺麗なPDFを作るためのものではなく、意思決定の軸です。
年齢や年収の表ではなく、「平日の19時、夕食後にどんな言葉で検索するのか」を想像できるかどうか。
ここまで行くと、LPの一文が変わり、CVRが変わる、そんな領域まで、マーケティングを突き詰める事ができます。
フェーズごとの正しいKPI設計

聞き馴染みのある単語。
KPIの話にも触れていきましょう。
KPIの設計を誤ると、事業そのものがねじ曲がってしまうことがあります。
通販事業の立ち上げ初期、
私は「月商200万円」という数字だけをKPIとして、社内に開示していた時期がありました。
通販事業はWEBマーケが初めての子たちも多く、
私は「わかりやすいKPIであること」を大切にしていました。
それが、月商200万円というKPI。
ところが、この数値目標を“唯一の正解”にしてしまったことで、スタッフは毎月セールを繰り返すようになりました。
結果的に「月商200万円」というゴールは達成するものの、その裏でセール後のCVRは低下し、LTVは毀損していったのです。
このケースは、スタッフが悪いのではありません。
彼らは与えられたKPIを忠実に追ったにすぎません。
問題は、経営者である私がKPIを誤って設計し、それをそのまま組織に開示してしまったことにありました。
KPIは単なる数値目標ではなく、「組織全体の意思決定をどの方向に誘導するか」というハンドルであり、
ブランドコンセプト同様、組織の力を一方向に向かわせるための言わばコンパスのような役割も持っています。
だからこそ、KPI設定を誤れば事業は望まぬ方向に進み、正しく設計すれば各メンバーの努力が自然と長期的な成長に収斂します。
それ以来、私はKPIを設計する際に「短期と長期の両立」を意識するようになりました。
例えば、売上だけでなく、リピート率やLTV、チャネル別のCACなど複数の指標を並べ、フェーズごとにどれを最重視するのかを明確に伝える。
また、ここで難しいのは、KPIは複雑にすれば良いというのではないと言うこと。
大事なのは、KPIを「組織の力を一方向に向かわせるためのコンパス」として活用すること。
リテラシーをひけらかしたり、メンバーの意思決定軸を複雑にして奪うものとして、
「KPIを壊れたコンパスにしない」「KPIを複雑すぎて理解できないコンパスにしない」ことも大切です。
そうすることで、メンバーが一時的な売上ではなく、持続的に利益を生み出す方向へ自然と動いてくれるようになります。
(余談ですが、ここではxmaindのようなマインドマップ系統のサービスが、KPI設計を整理するのに役立ちました。)
KPI設計とは「数字で組織をマネジメントする言語設計」です。
経営者がその精度を欠けば、現場の努力はむしろ逆効果に働きます。
逆に言えば、正しく設計されたKPIを正しく開示することこそが、組織を強くする最短距離なのだと、あの経験から強く学びました。
事業責任者がチャネルごとのCAC・PL・フリークエンシー・LTVを毎日把握すること

最後に強調したいのは「毎日数字を見る」という習慣です。
週次のレポートや月次会議では遅すぎます。
私は毎朝、売上、新規とリピートの比率、チャネル別のCAC、そして180日LTVとの差分、
つまりユニット貢献がプラスかどうかだけを確認します。
なぜ日次かというと、広告クリエイティブの勝敗は48時間で見えますし、在庫の推移も数日単位で未来を予測できます。
ここをリアルタイムで修正できるかどうかが、PLを守る最後の砦になる。
経営者が「数字を自分の目で直に見る」こと自体が、チーム全体に緊張感を生みます。
誰かがまとめたレポートではなく、一次データをそのまま覗くこと。
そこに現れる小さな異常値を見逃さないこと。これが事業を長期で伸ばす最低条件だと考えています。
まとめ
以上、経営を始め5年間、2事業立ち上げを行ってみて、
現時点で大切だと私が感じている事7選でした。
もっともっと成長して、また5年後には別の知見を持てていると良いなと思っています。
まだまだ成長してまいりますので、
今後ともソラノデザイン合同会社を、
何卒、宜しくお願い申し上げます。





