公開日:2025.07.20 更新日:2025.07.22
目次
SNSのオーガニックリーチの変化による、複数チャネル拡大へのすすめ。
いつもご覧いただきありがとうございます、ソラノデザイン、代表の角田です。
この頃、数年ぶりに頭がクリアです。
本日はホットなテーマ、SNSのオーガニックリーチの変化とその対策について、
真剣に書いていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はじめに

近年、SNS運用を取り巻く環境は急激に変化し、特にInstagramのオーガニックリーチが著しく低下しています。
かつてはフォロワーの15〜20%にリーチできた時代もありましたが、現在では一桁%にとどまるケースが一般的です。
本記事では、この変化の背景と課題を整理し、マルチチャネル戦略をいかに構築すべきかを提言します。
SNSオーガニックリーチの現状と背景
アルゴリズムシフトの影響
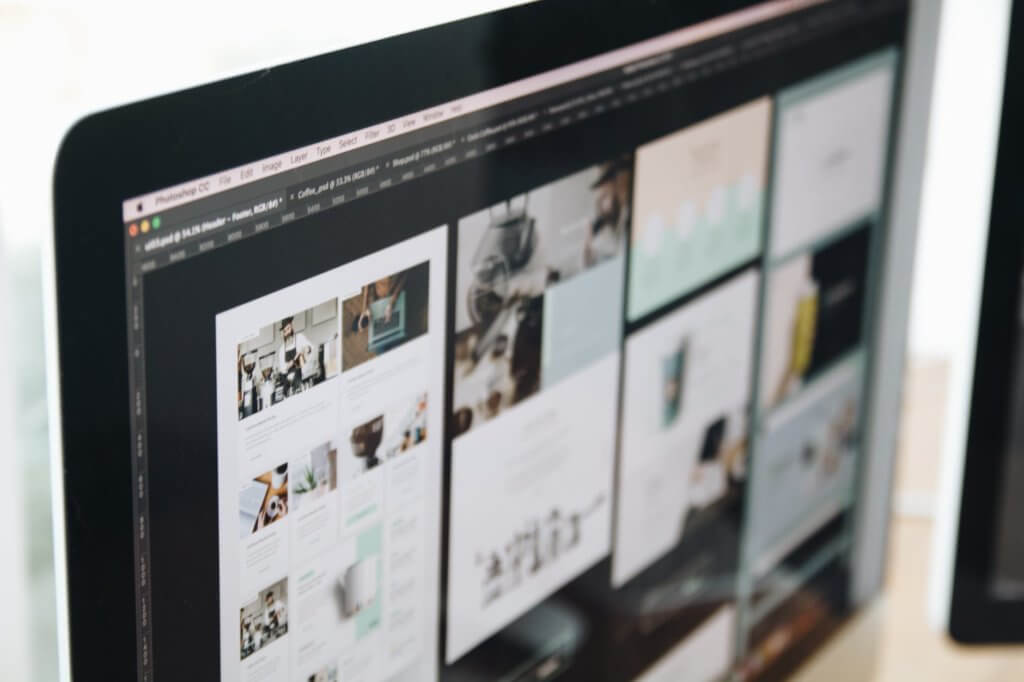
Instagramは2021年以降、プラットフォーム収益の最大化を狙い、フィードと発見タブの表示優先度を初動エンゲージメントに大きく依存する仕組みに変更したと言われています。
投稿直後30分〜1時間で獲得した「いいね」「コメント」「保存」「シェア」といった指標が一定数に達しないと、フォロワーのフィードや発見タブへの露出が抑えられ、結果としてオーガニックリーチが大幅に減少する現象が起こっており、近年事業化の皆様も、感じることがあったはずです。
一部では2025年以降、この動きは加速するとの見方もあり、時代に合わせた戦い方が必要になってきました。
結論、ソラノデザイン社は、
これからは
「集客チャネルは分散するべき時代」
「チャネル分散の流れが加速する時代」
が来ると読んでいます。
コンテンツ飽和と消費者行動の変化
また、今は1日あたり数千万件の投稿が生成される時代。
良質なコンテンツでも瞬時にタイムラインから消えてしまうのは当たり前です。
消費者側も「短尺動画」「カルーセル投稿」「ストーリー」のような多様なフォーマットを混在させたコンテンツでしか興味を惹かれなくなってきています。
その結果、従来の単一フォーマット中心の運用ではリーチ・エンゲージメントを維持できない状況が生まれてきているんですね。
オーガニックリーチ低下の定量的データ

では、定量的に時代を判断するためにも、
SNSでのオーガニックリーチの変化について、データを見ていきましょう。
リーチ率の推移
- 2019年:平均オーガニックリーチ 15〜20%
- 2022年:平均 7〜10%
- 2024年:平均 4〜6%
- 2025年:平均 3〜5%
このように半分以下に下落したデータが複数の調査会社から報告されています。
問題なのが、フォロワーへのリーチ率もほぼ同様の数字になっていることです。
2021年頃は、フォロワーの15~20%前後にリーチできるケースも珍しくありませんでした。
2025年にはInstagramビジネスアカウントの平均オーガニックリーチ率はわずか約3.5%にまで下落しています(YoYで12%減)
認めたくないですが、今はフォロワー数など何のKPIにもならない時代になってしまった、と言えるでしょう。
残念ではありますが、弊社も自社・クライアント様のSNS運用のKPIを、
2025年1月から変えました。
フォロワー数やCPF(フォロワー獲得単価)をKPIとしていた時代が今では懐かしいほどです。
業界別リーチ率の傾向
また、業界ごとのオーガニックリーチ率のデータも見ていきましょう。
- ファッションブランド:3.2%
- インテリア雑貨ブランド:約4.0%
- 飲食・フード系:約5.5%
例えば当社が通販事業を運営するインテリア雑貨は、もともとビジュアル訴求力が高くInstagramやTikTokをはじめとするSNSと親和性の高い業種でしたが、
それでも4%前後に低下しており、Instagram単体での新規リーチ獲得を自然流入だけで賄うのは、正直、ほぼ困難な状況です。
このようなオーガニックリーチの低迷により起こる課題が、
- 認知拡大の鈍化:新規フォロワー獲得が困難で、売上の頭打ちを招く。
- エンゲージメント維持の難化:既存フォロワーでも反応が得られにくく、ブランド関係性が希薄化。
- 広告依存度の上昇:オーガニックだけでは成果が出ないため、広告投資が増加し、ROI管理が複雑化。
などです。
これらの課題は単なる「運が悪い」では片付きません。
ビジネスマンたるもの、戦略的に打ち手を増やしていくべきです。
複数チャネル戦略の必要性

色々考えた結果、ソラノデザインとしての結論は以下の通りです。
2025年以降のマーケティングでは、単一チャネル依存を脱却し、
以下のように複数チャネルを組み合わせることでリスク分散しつつ、売上拡大を図ることが求められると、私は感じています。
今はそういう「時代」です。
時代に不満を言ってもしょうがないので、
具体的に、下記のような施策を行う必要があるでしょう。
有料広告への回帰
SNSをはじめとするプラットフォームでオーガニック流入を獲得することが正義とされていた時代が終わり、
広告モデルの時代に戻るのではと思っています。
そうなると当然、各種広告媒体の活用はマストです。
- Meta広告:リターゲティング広告で高CPAユーザーを再捕捉
- TikTok広告:低単価で高リーチを狙える短尺動画枠
- YouTube Shorts広告:検索流入との相乗効果
マイクロインフルエンサー様との連携
- フォロワー数千〜数万規模のインフルエンサー20~50名とアンバサダー契約
- UGC(ユーザー投稿)を自社ECサイトや公式SNSに自動掲載
- 複数コンテンツで多角的なブランド体験を提供
コンテンツの多様化
- カルーセル:How-toやビフォーアフター情報を保存したくなる形で提供
- リール:1分以内で視聴維持率を上げるストーリー型演出
- ストーリーズ:限定オファーやアンケートで参加率を向上
コンテンツ品質改善
- 投稿前にKPIを明確化(保存数/シェア数など)
- A/Bテストで見出しテキストやビジュアルを比較
- 月次レビューで高パフォーマンス投稿の要因分析
クロスチャネル連携設計
- Instagramリールの冒頭3秒フックとTikTok連動
- リール説明文内にブログ記事やYouTube動画への誘導リンク
- メールマガジンでLINE等プッシュ型のアプローチが可能なSNSに誘導
効果測定とPDCA
- Google Analytics/広告管理画面で流入元ごとのLTVを可視化
- 週次ダッシュボードでCPA・CPC・CVRをモニタリング
- 毎月のKPIギャップを共有し、施策微調整を迅速実行
また、各種SNSのオーガニックリーチが激減した現在、
SNS運用は単一チャネルの成功モデルからマルチチャネル統合モデルへと進化を迫られています。
例えば下記のような分散です。
- チャネル分散:Instagram+有料広告+マイクロインフルエンサー+メール・ブログ
- オフラインチャネルの設置
- コンテンツ多様化:リール、カルーセル、ストーリーズを連動させたシナリオ設計
- データドリブン:効果測定を細分化し、KPIギャップに即応
- コミュニティ形成:オンライン/オフラインイベントでブランドファンを育成
このようにマルチチャネル戦略をスピーディに実装し、
継続的なPDCAを回すことで、
プラットフォーム依存リスクを抑えながら安定した集客と売上拡大を行う時代が来たと言えるでしょう。
ソラノデザイン社も、資金調達から実店舗出店にすでに動いています。
これからの時代のデメリット
少し話はそれますが、これからの時代のデメリットとして、広告戦略で戦うには、
リピートモデルではない商材は毎日ROASを確認しながら広告を打つ、といった戦略が求められます。
実際にこれは今、私がやっているタスクですが、
このタスクを1年続けるのは本当に疲れましたし、楽ではありませんでした。
もし楽に稼ぎたい、というのであれば、
広告モデルが主流になる今後の2025年以降。
リピートモデルやストックビジネスのようなビジネスモデルが、今以上に最適でしょう。
もちろん考えることは皆同じなので、レッドオーシャンですが。。。
話を戻します。
対策として:オムニチャネル(オフライン活用)のすすめ

オフラインチャネルの重要性
デジタルマーケティング全盛の今、多くのブランドがオンライン施策に集中しがちですが、オフラインチャネルを適切に組み合わせたオムニチャネル戦略は、顧客接点の拡大と深いブランド体験の創出において依然として強力な武器になると考えています。
特にインテリア雑貨のように「実際に手に取り、空間に置いてみる」体験が重要な商材では、オンラインだけでは伝えきれない質感やサイズ感、空間への馴染みを直感的に感じてもらうことが欠かせません。
短期・小規模でテスト出店可能なポップアップストアなどは、低リスクかつ高レスポンスも期待できるでしょう。
ソラノデザイン社も実店舗ビジネスを行うと書きましたが、
最初は流石に、3ヶ月の期間限定出店でテストマーケティングを行う予定です。
オフラインチャネルは、以下のポイントを押さえることで、投資対効果を最大化できます。
- 立地選定:ターゲット顧客が集まりやすい駅ビルやショッピングモール、商店街の一角などを選び、小規模区画からスモールスタート。
- 期間設定:1週間未満~1ヶ月程度の短期集中で実施し、集客データを迅速に取得。3ヶ月のトライアルなら、1ヶ月単位で施策の改善を実行可能。
- 限定商品や体験要素:オンラインにない限定アイテムやワークショップ、フォトブースを設置し、来場動機を強化。
- OMO導線の設計:店頭でQRコードクーポン配布やLINE@登録誘導、ECサイトの店頭受取サービス(BOPIS)を用意し、オフライン来店をオンライン購買につなげる。
- リアルタイム分析:来場者数、購入者数、無人アンケート回収率などを日次で集計し、プロモーションや店内導線の改善に反映。
実店舗展開とショールーム化
常設店舗やショールームは、オンラインでは得られないブランドの世界観を体感してもらう絶好の場です。特にインテリア雑貨は、「空間を演出するアイテム」という文脈が重要であり、実際のコーディネート例を見せることで購買意欲を大きく刺激できます。
- コーナーディスプレイ:季節やテーマごとにインテリアを提案するコーナーを設置し、ワンストップで空間コーディネートを体験。
- パーソナルスタイリング:来店予約制でインテリアコーディネーターによる個別相談を実施し、顧客一人ひとりの好みやライフスタイルに合わせた提案。
- イベント連動:新商品発表会やクリスマスワークショップなど、定期的なオフラインイベントを開催し、顧客との接点を深化。
- 体験コンテンツ配信:店内で撮影した空間動画をInstagram ReelsやYouTube Shortsで配信し、オンラインフォロワーにもリアルな魅力を伝播。
イベント・ワークショップによるブランド体験創出
顧客自身が参加するワークショップやイベントは、双方向コミュニケーションを深めるうえで非常に有効です。特にファミリー層やインテリアに関心の高いコミュニティメンバーを招き、ブランドのファン化を促進できます。
- DIYワークショップ:木製雑貨の組み立て体験やペイント教室を開催し、完成後の商品を自宅に持ち帰ってもらう。
- 季節イベント:クリスマスリース作り、春のフラワーバスケット体験など、季節感を演出するコンテンツで集客。
- コラボレーション企画:地元カフェやギャラリーとのコラボで会場を拡大し、異業種の顧客層にリーチ。
- オンライン連動企画:イベント参加者限定のオンライン販売やライブ配信を実施し、オフライン体験をオンライン購買に誘導。
パートナーシップによるリアル販路拡大
卸売やコーナー展開などのパートナーシップは、初期コストを抑えながらリアル接点を増やせる方法です。特に大手ライフスタイルショップやセレクトショップへの納入は、既存顧客層との親和性が高く、ブランド認知を効率的に拡大できます。
- セレクトショップ卸:ターゲットに合致した店舗への限定コーナー設置。
- ホテル・カフェ導入:デザイン性の高いインテリア雑貨を客室や店内で使用してもらい、顧客体験を通じた認知拡大。
- 企業ギフト提案:ノベルティや福利厚生ギフトとしての卸売プランを用意し、法人顧客との関係構築。
OMO(Online Merges with Offline)施策の徹底
オフラインとオンラインをシームレスに連携させるOMO施策は、顧客の購買体験をスムーズにし、リピート率やLTV(顧客生涯価値)の向上に直結します。
- BOPIS(Buy Online, Pickup In Store):ECサイトで購入した商品を最寄り店舗で受け取れるサービスを提供し、来店機会を創出。
- 店頭体験からEC誘導:体験スペースに商品QRコードを設置し、スタイリング動画や商品詳細ページに即アクセス可能に。
- オンライン限定クーポン発行:店頭イベント参加者にのみ配布するECクーポンを用意し、オフライン来店からオンライン購買を促進。
- 会員データ統合:POSとECの顧客情報を連携し、来店履歴・購買履歴を一元管理。パーソナライズドDMやLINE配信でアプローチ。
効果測定とKPI設計
オフライン施策の効果を定量的に把握するためには、適切なKPI設計と計測環境の整備が不可欠です。
- フットフォール測定:来場者数カウントセンサーやQRコードスキャン数で可視化。
- 転換率(CVR):来場者数に対する購入者数、アンケート回答率、クーポン利用率など。
- 客単価(AOV):店頭売上÷購入者数、オンライン・オフラインの比較分析。
- オフライン→オンライン回遊率:QRコードリンク経由のECアクセス数、LINE会員登録数。
- LTVモニタリング:店頭・EC両チャネルの累積購入額を顧客ごとに追跡。
実行フローと運用体制
オフライン施策を継続的に運用し成果を最大化するには、明確な役割分担と運用フローを構築することが重要です。
- 企画・マーケティングチーム:出店戦略立案、パートナー交渉、イベント企画。
- 店舗運営チーム:什器設営、接客オペレーション、在庫管理。
- データ分析チーム:KPI設定、分析ダッシュボード構築、改善施策提案。
- 顧客対応チーム:チャットボット・有人サポート、アンケート回収・フォロー。
- 連携ミーティング:オンライン・オフライン担当が週次で数値共有し、改善アクションを即実行。
まとめ
複数チャネルへの分散、オムニチャネル戦略が必要とされるであろう2025年以降のビジネス。
オンラインとオフラインの強みを掛け合わせることで、顧客のあらゆる接点で一貫したブランド体験を提供し、競合優位性を確立する方向が、最適解だと今の所考えています。
特に実店舗などのオフライン施策は、ユーザーに世界観を五感で体感してもらう絶好の機会となります。
マルチチャネル戦略成功に向けて、色々とこれからも情報を発信していこうと思います。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。



